先週から今週にかけ、日経平均は3万円台を一時回復するも急落。
TOPIXや個別銘柄は踏ん張っている様子も見受けられましたが、連日の下落にやや崩れた感もあります。
ここからの戻りは、二極化して「まだら模様」になりそうな気配です。上昇トレンドがまだ崩れていない銘柄と、調整入りした銘柄の違いを探りました。
先週から今週にかけ、日経平均は3万円台を一時回復するも急落。
TOPIXや個別銘柄は踏ん張っている様子も見受けられましたが、連日の下落にやや崩れた感もあります。
ここからの戻りは、二極化して「まだら模様」になりそうな気配です。上昇トレンドがまだ崩れていない銘柄と、調整入りした銘柄の違いを探りました。
相場の予測を高い確率で当てるのは至難の業……必然的に、損を小さく抑えて利益を伸ばす、損小利大のテクニックが求められます。
でも、ただ頑張るだけでは実現しません。
必要な3つの条件を紹介しました。
3万円の大台回復を目前に日経平均が足踏みする一方で、一気に新高値を取ったTOPIX。
循環物色が衰えないなか、押し目からの切り返しで、主役は入れ替わった感があります。
ここに来て日経平均が3万円台を回復。いよいよ大相場へと向かうのか、個別銘柄の動きを丁寧にウォッチしました。
日経平均株価が膠着するなか、循環物色が広がる個別株。
次のステージへ向けて飛び立つためには、保合ブレイクが第一条件となりそうです。
反騰の兆しを逃さないためには、どんな値動きに注目すればよいのか──個別銘柄の値動きを見ながら考察します。
日経平均が3万円、バブルではないか、目先の天井ではないか──。
弱気論、暴落警戒論がありますが、私は目先も強気です。
個別銘柄を観察していると、いわゆる「食い散らかした感」がないからです。
3月8日の放送では、そんな強気の見通しを前提に、「ここから買うなら、こういう銘柄か」という視点で市場を観察しました。
映像は、「YouTubeチャンネル「マーケット・スクランブル」」でご覧ください。
(まだ押し目を待つのか、もうここから攻めるのか)

3月8日の放送は、1週間前の3月1日収録で、ご覧に入れたチャートは2月末まで。
というわけで、紹介した11銘柄がその後どう動いているかをベタにチェックしてみましょう。
まずは、「高値圏で押し目」と分類した銘柄。
再び切り返して上昇するのではないか、上げ止まっている可能性もあるものの買い目線を外せないのではないか……こんなニュアンスでピックアップした3銘柄です。
※青いタテ線以降が、その後3月10日までの動きです(以下10銘柄すべて同じ)。
※赤が買い線、黒が売り線、中源線ルールで判定しています。
2531宝HDは、私も実際に中源線で売買しています。
ほぼ1年間上げているので、本来は陰転(赤→黒)を見て「下げで取れるか」と感じるところですが、相場つきから安易に弱気になれないと考えています。とりあえずシグナルどおりに1単位売り建てしていましたが、3月2日に裁量で買い戻し、現在はポジションなしで陽転待ちという状況です。
6728アルバックは、宝HDとは対照的に、中源線のとおりに下げ基調です。
一部の銘柄が上げ止まってきたか──こんな観測もあるでしょう。
8078阪和興業は、グイッと切り返して中源線が陽転(黒→赤)し、続伸して1月の高値をブレイクアウトしました。こういう動きがあるんですよね。
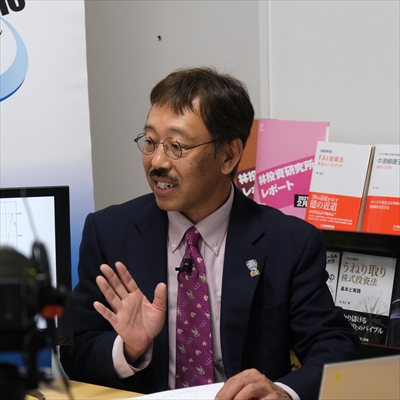
次の銘柄群は「保合をブレイク」と分類したものですが、最初の分類と比較すると、「上昇してきたが、まだ中段にいる」という印象のものです。
1518三井松島HDは2月に陰転(買いポジションを利食い)しましたが、素早く切り替えして再び陽転しています。中源線の特別ルール「再転換」によって、最初から2単位買っています。そして、押し目で1単位増やして満玉(3単位)のあと、上伸しています。
4331テイクアンドギヴ・ニーズはブライダル事業の会社で、コロナ禍のなか大きく売られました。材料から「とうぶんダメだ……」なんて観測もあるでしょうが、上がるときは上がるのが相場です。「アフターコロナ」なんて解説もあるでしょうが、そんな後講釈に耳を傾けてはいけません。
中段の銘柄の最後は、7860エイベックスです。
ご覧のように、12月にスタートした上昇の勢いは衰えていません。
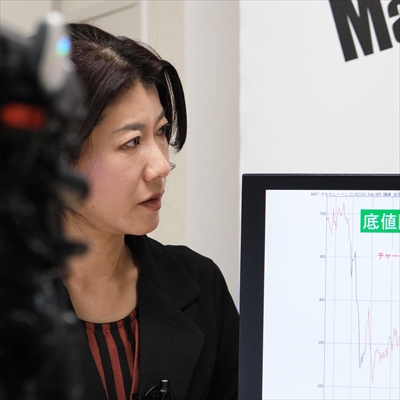
3つめの銘柄群は、おそらく個人投資家が最も好む「出遅れ」的なものです。
2768双日は、日商岩井とニチメンが合併した総合商社です。
米国の著名投資家ウォーレン・バフェット氏は買っていないようですが、いわゆる割安感もあって、多くの個人投資家が「じっくり保有」なんて捉え方をしているかもしれません。価格帯が低い銘柄は、変動率が意外と大きいのが魅力です。
8219青山商事は、コロナでスーツ需要低迷が加速し、大幅な減収減益、赤字転落という状況ですが、スーツ離れは以前からのことで、実際に2018年からずっと下げ傾向です。今後は、店舗、人員、顧客リストといった“財産”を活用して事業を再構築していくのでしょう。とりあえず、売られすぎの反動で「まだまだ上昇途中」との声もけっこうあります。
最後は、かなり後発組の3銘柄です。
6430ダイコク電機、6355住友精密工業、8897タカラレーベンの3つですが、タカラレーベンが最も元気ですね。
出遅れ狙いは私も好きですが、安心感があるわりにはスカッとした結果が出ないケースも多いのです。「出遅れ出ずじまい」という言葉もあります。そういったザンネンな結果も想定しておく必要があります。
また、出遅れ銘柄が軒並み物色されるようなときは、先発組が次々と上げ止まっていると考えることもできます。日経平均ではなく、丁寧に個別銘柄を観察して戦略を練ってください。

マーケット・スクランブルのレギュラー放送は現在、第1週と第2週ですが、先月から第3週に「フォローアップ番組」をお送りしています。
今回取り上げた11銘柄から、おもしろい観点を拾ってお届けします。
3月15日(月)の夜8時、お楽しみに!

2020年12月新刊
3月8日放送のフォローアップを、「週報」に掲載しました。
※「中源線研究会」に登録のみなさんには、メールでも配信しています。
→登録はこちら(無料)
番組タイトル: まだ押し目を待つのか、もうここから攻めるのか ~これから買える銘柄~
相場格言「売るべし 買うべし 休むべし」の意味は、「休みも重要である」と説明されますが、もう少し突っ込んで考えてみました。
本日公開の動画、「5分で学べる株式投資・トレード」。
1000円を超える日経平均急落で、にわかに投資家心理を脅かす「コロナバブル」の崩壊。
だが、ここからの切り返しで、いよいよ低位株、バリュー株の巻き返しが期待されます。
初動を逃さないためには、どんな値動きに注目すればよいのか、立ち上がった銘柄をヒントに考えました。
→ 動画の視聴はこちら(林投資研究所YouTubeチャンネル)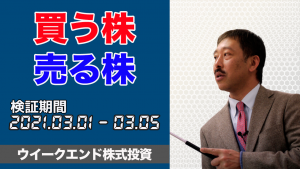
日経平均が3万円に乗せたことを受け、暴落を懸念する声が高まっています。
しかし、そこにどのような根拠があるのでしょう……私には疑問です。
毎月第1週は定点観測。3月1日の放送では、先月につづいて強気の姿勢を紹介しながら、8銘柄の定点観測を行いました。個別銘柄の状況は、どうなっているのか?
映像は、「YouTubeチャンネル「マーケット・スクランブル」」でご覧ください。
コロナバブルが弾けた? ~上げ相場がまだ終わらない理由

番組でもコメントしたとおり、現在の日本の株式市場について、暴落を警戒する必要は全くないと考えています。
「バブルか、バブルでないか」という論点で、新聞記事やテレビ番組が作られていますが、そんな議論をする根拠が存在しないと思うのです。市場全体のPER(株価収益率)やPBR(株価純資産倍率)も特別に大きな数字ではなく、むしろ割安ともいえます。
根拠を実感できないバブル論や暴落説に対して必死に反論するのもむなしいので、あまりやりたくありません。私が目先も強気の姿勢でいる根拠は、個別銘柄の騰落状況です。番組をなぞるかたちで次項で述べることにして、ここでは「なぜ下げを懸念する声があるのか」を考えてみましょう。
上げ下げがあるのが相場なので、そもそも下げを極端に怖がる必要はありません。
個人投資家は売買に特別な制約を受けないので、持ち株を減らす(キャッシュポジションを高める)ことで下げによる被害を軽減できます。手持ち株をゼロにしてもいいし、下げで利益が出るカラ売りを積極的に仕掛ける選択肢だってあるのです。
では、下げ相場を悲観するだけでなく、上げ相場の最中に決まって暴落説がささやかれる理由は? 少しひねくれた観点を紹介します。
ウケのいい相場情報をつくるには、最も厚い層を狙うのが正解です。平均ではなく分布が厚い層、すなわち、常にヤラレ玉を抱えていて「上がってくれ~」と願っている投資家層です。
だから、下げた日には「先物売り」とか「利食い売りで反落」といった決まり文句で、まるで「下がってゴメンね」と言わんばかりの表現を使います。株価を支える約束でもしていたかのように……。下げの解説では、「機関投資家の持ち高調整」なんて表現も決まり文句のひとつですが、機関投資家はそれほど機敏に持ち高を調整したりしません。
「日経平均3万円」が特に意味のある節目ではないのですが、ちょっとザンネンな投資家の傾向として、常に不安で外部に正解を求めるということが挙げられます。そんな気持ちに迎合するには、「3万円」というキリのいい数字が絶好の材料(エサ)なのです。「日経平均3万円、これからどうなる」と書けば、多くの人が読んでくれます。

昨年いらい上昇している個別銘柄は、意外と限定的です。
例えば、最も顕著に上がっている銘柄のひとつは、次に示すソフトバンクグループ(9984)です。
コロナショックの安値から3倍になっていますが、すっ飛ぶような上げ方をしている期間はありません。また、十分な上げの日柄を経て「こんどは下げか?」と思わせながらも下げず、再び上昇がスタートするのです。この手の銘柄がそろそろ上げ止まってきた可能性はありますが、現時点ではカラ売りで取れている状況にありません。
そして、これまで動きのなかった銘柄も物色されはじめました。
例えば、次に示すテイクアンドギヴ・ニーズ(4331)です。
ウエディング事業がメインなので、コロナ禍で大きく売られました。そして、1年近くも安値を這っていました。それが、2月になって動いてきたのです。売り上げは以前の数分の1に落ち、赤字予想はそのまま、無配転落という状況ですが、突然に人気を集めたのです。元来しっかりと利益を出している会社ですが、「アフターコロナ」をキーワードとする急回復の期待が“あと出しの材料”なのでしょう。
ただ、こういった動きをみせているのは、まだ一部分の銘柄にとどまっています。
個別株の騰落を見ると、いわゆる「食い散らかした感」など全くありません。むしろ、多くの市場参加者が、上げに乗れずにイラついている空気が漂っていると思います。
買いたいのに買えない、下げてほしい──いわゆる「買いたい弱気」に迎合する意味でも、暴落論はウケるのかもしれません。

相場は「まだ過熱していない」と述べましたが、そんなことを言っているうちに物色対象がジワッと広がり、いつのまにか上げのエネルギーが弱まっていたりするのも相場の現実です。
ひと月前、2月1日の放送で、私は強気を述べました。そして、とりあえず当たっています。でも、弱気から強気に転換する市場参加者が増えたあと、上げを予見した者が天井を見極められるのかというと、そんなこともありません。逆に、熱くなって冷静さを失うかもしれません。
上げ相場は、買い方がつくります。上昇の見込みを立てて参加者が増えることで株価が上がり、それを見て次の参加者が集まる──こういう図式です。では、下げ相場は売り方(下げを見込んでカラ売りを仕掛ける向き)がつくるのかというと、そうではなく、買い方が増加するペースが落ちることで上がらなくなり、ちょっとしたきっかけで下げはじめます。そして、それを見た買い方の投げが、下げを加速させるのです。
いくら経験があっても、感情をもつ人間である以上、心が熱くなってしまうものです。昨今は、心理学的な考察によるプロスペクト理論なども知識として身近ですが、理屈を知ったからといって、行動スタイルを理想に近づけることは難しいものです。
この問題は、相場の永遠のテーマです。
だからこそ、ちまたの情報に安易に飛びつかないことが大切です。かるいノリで正解さがしをしないよう、常に気をつけたいのです。

私が相当な“当たり屋”だったとしても、ずっと相場を当てつづけることは不可能です。だから、とりあえず当たっているといっても、「では、オレも買おうか」と反応してはいけません。
今回、暴落説を否定することで伝えたかったのは、無責任な情報が多い現実と、自らの意思をもって売買することの大切さです。
私の強気論に確信をもって同調するなら問題ありませんが、安易に飛びつかないことです。上か下か、買いか売りか……二択を当てるのが相場ではありません。「わからないからポジションを取らない」というのも、とても重要な選択肢だと認識してください。
「決めかねるけど、どちらかというと買い目線」くらいの感覚で、試し玉だけを維持する、なんて取り組み方もあります。
ちなみに、番組で紹介している「中源線」は、トレンドを機械的に判断して3分割の売買まで示してくれますが、きわめてシンプルなルールは、利用者のアレンジを可能にしています。いえ、可能どころか、率先して「自分の道具として使う」ことを促しています。
観点や基準が定まらない銘柄情報を疑い、経済記者が示す観点に左右されることもなく、感じるままに売買する、自分が思っているとおりにポジションを動かすのが相場です。そのための基本形はなにか──そんな考察をしてみてください。

来週3月8日は、テーマ別の番組、「押し目を待つか、ここから攻めるか ~これから買える銘柄」というタイトルでお送りします。お楽しみに!
2020年12月新刊