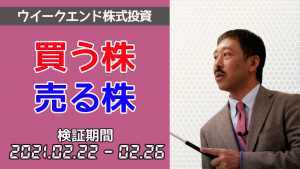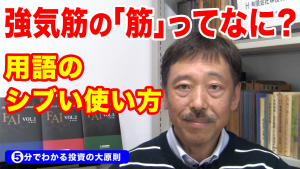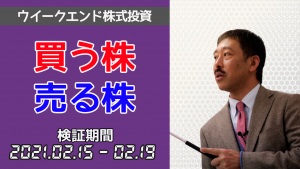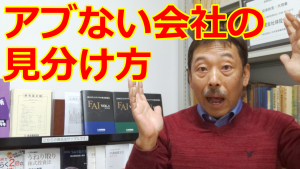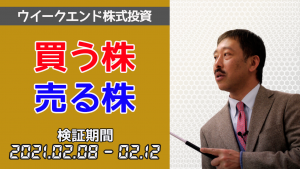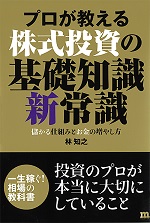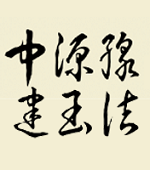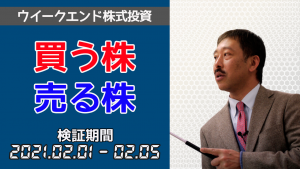好評のWEB読みもの第10弾、「手描きチャートと変動感覚」の後半を本日、公開しました。
Author Archives: kanrisya
潮目が変わったのか、ほどよい押し目か
3万円の大台をスルスルと上抜けたあと、目先調整局面にある日経平均。
ほどよい押し目で切り返すのか、それとも久しぶりの深い調整となるのか。
目下、売り線となっている銘柄を取り上げ、今後の展開を詳細に考察しました。
強気筋の「筋」ってなに?
「5分で学べる株式投資・トレード」シリーズは、いつも5分で終わりません……でも、今回はちゃんと5分です(笑)。
「強気」と「弱気」の意味と使い方、強気筋の「筋」とはなにか、そして売買するうえでの適正な考え方を紹介しました。
【新番組】売り銘柄、買い銘柄の検証
やっと来た押し目? 問題は深さとタイミングだ!
ウイークエンド株式投資2月19日。
3万円の大台を挟んで、急ピッチに上値を追った日経平均。
押し目を待っている投資家にとってはイラ立つ展開だったかもしれません。
週の後半はさすがに一服、押し目形成しそうですが、「兆し」は今週前半、日経平均が最高値をつけた2月16日に出ていました。
アブない会社の見分け方
日経平均3万円 ~もう一段上を目指す手掛かりは…
あれよあれよという間に、日経平均は3万円目前。
ここにきて、出遅れの物色や小型株の巻き返しが目につきます。
【3万円突破】もう一段上を目指すには、どんな流れが必要なのでしょうか。
2月8日放送のフォローアップ
林 知之
個人投資家に最適なヘッジ売り
私は、株式市場に対して強気です。
中長期で上げだと考えていますし、目先の2月から3月にかけても「買い目線」を維持できないかと感じています。
そんな個人的な見通しは別として、相場である以上、上げ下げはあります。
私の予測が当たったとしても、物色の対象が広がって買い一巡すれば、全体的に下げる局面もあるでしょう。個別の上げ下げは、当然のように起こります。
下げ相場において個人投資家が打つべき手は?
どんなことがポイントなのか?
2月8日の放送では、実践論をわかりやすく解説しました。
映像は、「YouTubeチャンネル「マーケット・スクランブル」」でご覧ください。
(日経平均はどこまで上がる? 株価急落前に打つべき最善手)

指数でヘッジできるか
複数の個別銘柄を保有した状態で、多くの投資家は急落を警戒します。
株式市場では、「○○ショック」と呼ばれる突発的な下げがあり得るからです。
「暴落時の対応は?」と問われ、「日経平均を売り建てする」と答える投資家も多いようです。
先物でなくても、日経平均に連動するETF(上場投信)やCFD(差金決済取引)を利用すれば実行はカンタンです。手持ちの現物はそのままに別途、日経平均が下がると利益が出るポジションをつくればいいのです。
でも、こういった方法が本当に値下がりをヘッジ(損失のカバー)するのでしょうか?
「現物の保有」に「指数の売り建て」を追加した場合、以下に挙げるような問題が気になります。
-
- 機能するとはかぎらない
保有銘柄とヘッジの指数売買が連動するのか?
- 機能するとはかぎらない
-
- ヘタをすれば「股裂き」になる
保有銘柄は下落、売り建てした指数は上昇……こんなオチも“あるある”
- ヘタをすれば「股裂き」になる
-
- ほぐすのに苦労する
両建ては予想外に複雑……どうやって外していくの?
利食いの両建てでも、ほぐすときに苦労しますよ
- ほぐすのに苦労する
-
- 思いつきでやっていませんか?
上記のようなことを真剣に考えた戦略ではなく、下げに遭遇して、慌てて思いついた対応であることが多いようです……要注意!
せっかく買った銘柄を手放したくない、個別銘柄を細かく動かすのは手間だ、ちょっとカッコいいことをやってみたい──こんな心理が誰にでもあるのですが、もっとシンプルに考えてみてはどうかというのが、私からの提案です。

ポジションを「ほぐす」とは?
前項で述べた「ポジションをほぐすのに苦労する」という部分には、疑問をもつ読者もいると思います。
まずは、単純な手仕舞いを考えてください。
- 買って上がったから手仕舞いする(利食い)
- 買ったら下がった……見切りをつけて手仕舞いする(損切り)
利食い手仕舞いは、ルンルン仲良しの恋人と別れるようなもの……明確な理由を見つけにくいのです。一方の損切りは、「このポジションはダメだ」と手仕舞いする理由は明確なのですが、自分自身で負けを認めることに抵抗を感じます。やはり難しい……。
いずれにしても、つくるのはカンタン、捨てたり壊したりするのは難しいのです。
買った銘柄が上がったので、「利益確保」を狙って両建てにする(買いポジションは維持したまま、同じ銘柄をカラ売りする)──そのあと、どうするのですか? 値動きを見ながら臨機応変に売り買いして利益を積み上げていくという狙いでしょうが、混乱して余分な売買をしてしまうことが懸念されます。
日々の値動きや大量のニュースによって、ただでさえ混乱しがちなのが株式投資・トレードという行為です。その波に巻き込まれないようにするには、よほどシンプルな行動指針が必要です。
少なくとも、自ら複雑な状況をつくり出すなんて得策ではありません。

魔法の「ポジションゼロ」
相場の世界には、さまざまな人がいます。売買で生活している「相場師」(トレーダー)から、コツコツと資料を作るアナリスト、現場で日々、投資家と接している営業マンなど。総称して、「業界人」としましょう。
業界人が口をそろえて言うのは、「一般投資家は、売買をやりすぎる」という言葉です。
株数が多い、資金稼働率が高い、そもそも資金の額が多い、情報に敏感すぎる等々。
「今日はこれが上がった。次はなんだ」
「買っておけばよかった。こんどは取り損なわずに儲けたい」
機会損失を嫌うあまり、やりすぎてしまうのです。
なんとなく違和感を覚えても、前述したように「ほぐすのが難しい」ので、ポジションは積み上がりやすいのです。意外と簡単に限界を超え、動けなくなります。
ぜひとも、「ポジションゼロ」という状態を、アイデアとして頭にキープしておいてください。
機関投資家とちがい、私たち個人投資家には、「こうしなければならない」といった課題がないのです。気分が乗らなかったら、仕事が忙しかったら、自分の好みの相場つきでなかったら、手を出さずに見ていていいのです。
機関投資家は、決められた資金を最大限効率よくまわすため、ギリギリの線までポジションをつくります。そして毎日、その管理に大きなエネルギーを費やします。でも、個人投資家がそのマネをする必要などありません。いや、マネするべきではないのです。
まずは大きく負けないこと。そのためには、「機会損失」なんて言葉を気にせずに余分なことをしない習慣を身につけるのが第一です。そして、「ここだ!」と思える場面でスルスルッと出動し、サクサクッと撤退して利益を残す。
個人投資家の資金は、数十万円、あるいは数百万円か数千万円、かなり多くても数億円でしょう。緻密に計算したり、難しい技を使う必要はなく、上手にメリハリをつけることで高効率の運用が可能だと考えてください。
個人投資家にとって、全くポジションのない状態である「ポジションゼロ」(「マル」とも呼ぶ)が、実はニュートラルポジション、ホームポジションなのです。この発想を大切にして、常にスムーズに押したり引いたり、攻めたり守ったり、自らを完全にコントロールしている状態を維持してほしいのです。

堂々たるドテン 中源線の特長
番組で取り上げている中源線(中源線建玉法)は、上げ下げの判断を明確に出します。
上げから下げへの転換(陰転)、下げから上げへの転換(陽転)の際には、スパッとポジションをひっくり返します。売り買いを逆にすることを「ドテン」といいますが、相場なので“朝令暮改”よろしく「やっぱり買いだ」「いや、売りだった」と判断を覆すなんて当然のこと。この現実を無視しないので、両建てなんて中途半端なことは規定にないのです。
そのかわり、資金稼働率が定められているうえに、3分割でポジションを動かします。
こうして全体にバランスよく組み立てられているので、いっさい混乱を生まないシンプルな行動が成立します。実際に利用すると、多くの投資家は、「なるほど、落ち着いている」「これなら継続できる」と納得します。
機械的判断に従う売買では、「えっ、ここで売り?」みたいに、ちょっとキモチわるい場面もあるのですが、人間の判断のようなブレが全くありません。小さなブレが重なって大きなケガになる、そんなケースは考えられないわけです。
ペン習字のお手本のように、中源線どおりの売買をすることで、プロが理想と考える臨機応変かつ堂々としたポジション操作を体験・体感できます。「うまくつくられた売買ツールであると同時に、最高の練習道具」と評価される理由がここにあります。

フォローアップ第2回は、今回のテーマをさらに掘り下げて考えます。お楽しみに!
※番組フォローアップ(2)は、「中源線シグナル配信」(対象:全上場銘柄)の会員限定のブログに公開し、同時に会員限定でメール配信も行います。
2020年12月新刊
2月8日放送のフォローアップ
2月1日放送のフォローアップを、「週報」に掲載しました。
番組タイトル: 日経平均はどこまで上がる? 株価急落前に打つべき最善手
急落後の戻り歩調 ~一時的な下げをどう評価するか
先週末、1月28日、29日の2日間で約1000円下げた日経平均。調整局面入りの兆しとみるか、急ピッチで上げてきた日経平均がスピード調整しただけとみるか。
強弱論争は不毛ですが、相場全体の変化を冷静にみる対応は必要です。今週は「N字の切り返し」に着目しながら、市場の変化、個別銘柄の値動きをダイジェストしました。