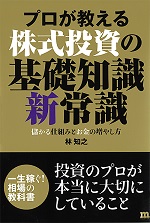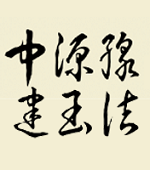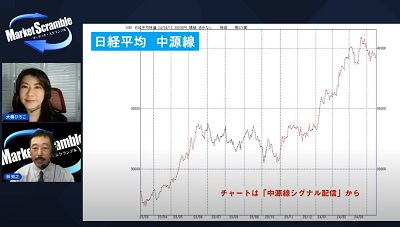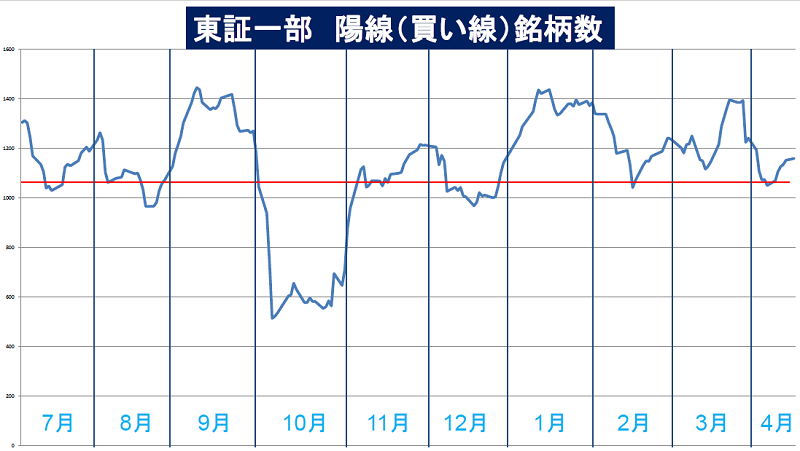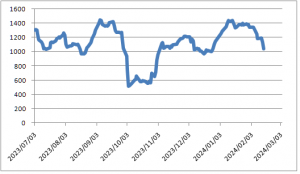冷静な目で銘柄を入れ替えるべし
株式市場全体の環境は、良好な状態が継続していると考えます。
でも、3月決算の発表を受けて買われる銘柄がある一方、ネガティブな評価でトレンドを崩す銘柄が目立っています。
映像は、YouTubeチャンネル「マーケット・スクランブル」でご覧ください。
改めて意識されるバブル高値~ブレイク前に買いたい8銘柄

春高
私は毎年、「春高」という観点で相場を評価します。
必ず春に高い、とは決まっていません。
むしろ逆のこともあります。
それを踏まえて、とりあえず「春にはぼちぼち買われる」という前提で、個別銘柄を幅広く観察します。
今年はどうだったか。
先月のフォローアップでも触れましたが、年初から日経平均が大きく上昇しました。
そのわりに、個別銘柄の伸びはありませんでした。
ところが、隅にある意外な銘柄まで適度に買われた感もあったのです。
マーケットの環境はわるくない──3月決算が出そろったところで、あらためて人気化する個別銘柄が出現すると期待していましたが、現時点では、むしろ逆の流れです。
決算発表後に買われた銘柄もありますが、それほどわるくないのにネガティブな評価を受けて売られる……そんな銘柄が目立つ気がします。
私が見ている範囲が偏っているのかもしれませんが、実際に中源線の分析を見ていると、「指数が強くて個別が弱い」という傾向が表れています。

読みの限界
長い間、相場を見ていますが、例えば長期的な安値圏にある2つの銘柄が同じような条件なのに、ひとつは低迷をつづけ、もうひとつは人気化して大暴騰、なんてことがあります。
これを当てる? いやいや、ムリなんです。
それがわかったら、とっくの昔に私ひとりでこっそり、すべての市場が壊れるまで儲けて、世界一の金持ちになっていますから。
結局は、“とりあえずの結果”を見て、対応していくしかないのです。
いわゆるポジション調整、ポジション操作です。
私たちには感情があるので、「できのわるい子ほどかわいい」なんて心理があります。
学校のクラスに成績のよくない子がいたら先生は、立場的にも心情的にも放っておけません。
でも、私たちが相手にするのは、単なる株の銘柄です。
ただの“カネ儲け対象”でしかないのです。
できのわるい子をかわいがるなんて感覚を持ち込まず、冷たく捨てるのが正解です。

プロが行う一歩遅れ
できのわるい子を冷たく捨てる──たぶん、社会人としての行動規範、道徳みたいなものを少しでも持ち込むと、実行しにくいのだと思います。
そんなつもりはなくても、つい持ち込んでしまうのです。
解決策はひとつ!
「儲かるトレーダーを演じる」という感覚をもち、常にそれを手放さないことです。
家族といるときはリラックス、でも、家族一人一人を守るつもりで状況を見ています。
言葉はカジュアルです。
同じ人間が仕事場に行くと、キリッとした表情で、スキのない敬語を使うでしょう。
2つの言語を話すバイリンガルどころではありません。
誰もが、かなり器用な“切り替え”を、無意識に実行する能力があるのです。
スゴいことです。
だから、相場のことを考える際は、俗世間から離れてキリッと、“相場モード”になるべきです。意識するだけで、誰でもできちゃいます。
利益を上げている上級者も、プロも、同じ人間です。
感情や心理は、初心者と同じです。
結果に差があるのは、売買行動の決め方、そのプロセスを意識していることだけです。
上がると思って買った銘柄が弱含み……「今売ると損が確定する」=「自分がバカだったと認めなければならない」と思うのは、同じです。
でも、「イヤなんだけど、このポジションは現金化して、ほかのチャンスをさぐるのが正解だよな」と気持ちをまとめ、淡々と損切りを実行に移します。
この行動を支えるのが“相場モード”です。
「自分は儲かるトレーダーだ。ほかの人ができない行動を、ビシッとやるんだ!」という意識、「本来の正直な行動ではないけど、そんな行動を取る人物を演じるんだ」という気構えです。

予測を当てずに結果を出す
予測を当てる必要はありません。
もちろん、ポジションのもととなる予測が100%曲がったら、利益のチャンスはゼロです。
でも、そんなことは起こりません。
サイコロをころがしたって、上か下かの予測は50%当たるのです。
だから、必死に考えても、50%を少し上回る程度の的中率が限界です。
そして、前述したようなポジション調整が必要なのです。
ポジションをつくったあと少し時間が経過すると、とりあえずの答えが出ます。
「どうやら予測が当たったようだ」とか「なんか見込み違いな気がする」とか。
これを受けて、“ダメな子”をバサッと切って、“よい子”は大事に抱えておくべく、ポジションの調整、銘柄の入れ替えを行うのです。
5月に入り、株式市場全体は水準を保っています。
でも、株価指数も個別も“熱い”動きはみられません。
3月決算が出そろって、なんとなく新しいトレンドがはじまりつつある感じです。
落ち着いて観察し、“よい子”と“わるい子”を自分なりに見極めましょう。
予測が当たったか否かは、ただの過去の話です。
未来を見据えて、自分の手の内を、コツコツとよいかたちに整えるのが相場という行為です。

2020年12月新刊