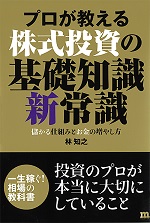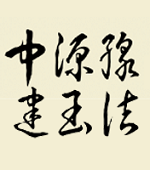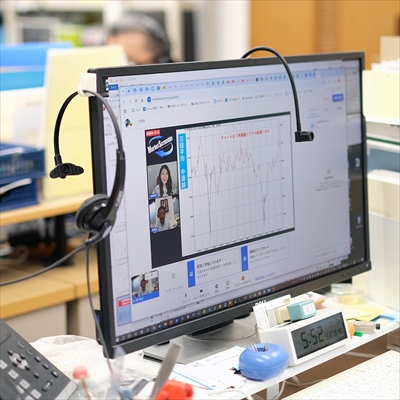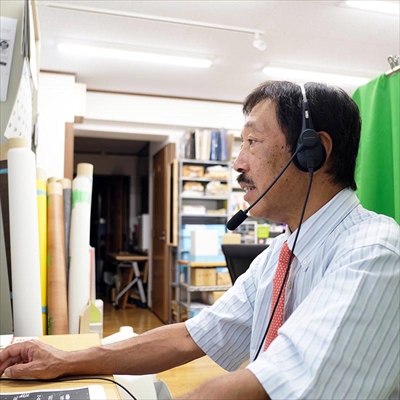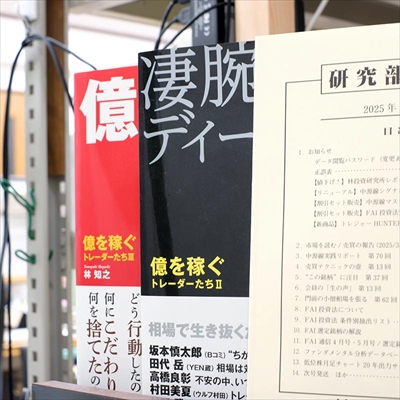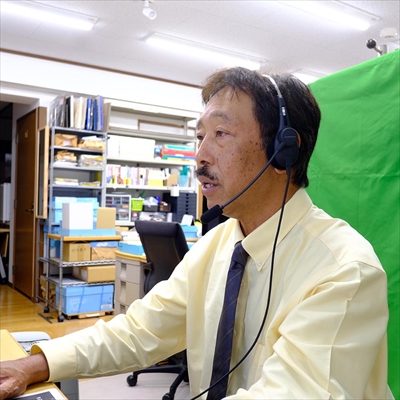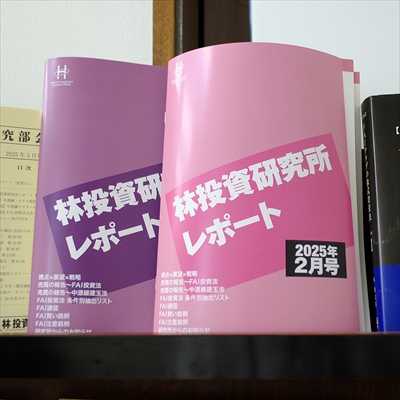材料張りの悲劇
映像は、YouTubeチャンネル「マーケット・スクランブル」でご覧ください。
ここから狙える、じわり上昇トレンド8銘柄

雇用統計で一喜一憂
米国の雇用統計(2025年7月分)が大幅に下方修正されたことが、マーケットでは話題となっています。でも私は、気にしていません。雇用統計のデータが日本の株式市場にどう影響するのか、具体的にどんな対応が有効なのか、方程式らしきものをイメージできたことはありません。今後も、考えないと思います。
今回の雇用統計の悪化について、一部では、公的部門の人員削減や、回答率の低下といった要因があると指摘されています。
また、関税の影響が不透明であるとの判断から製造業が雇用を一時的に抑制していることも考えられます。しかし、関税を武器に外交を継続し、多くの国から米国への投資を促し、ひいては、米国内産業の再構築、発展や雇用増など将来への期待がもたれているのが現状ではないのでしょうか。
雇用統計の悪化で暴落の危機……いつものように、“材料のための材料”だと感じました。

売りが多かった?
株価が下落した際に、「売りが出た」という表現を目にすることがあります。
でも、株価がついている=売りと買いが同数あった、ということです。
もしも売買動向を正確につかもうとするなら、売買に参加した全員に「なぜ、この銘柄を買ったのか?」「なぜ、3千株ではなく千株だったのか?」と聞かなければなりません。また、売買しなかった全員に、「なぜ売買しなかったのか?」と根掘り葉掘り質問しなければなりません。不可能です。
そもそも、直近過去の動きを見て「変動の理由」をさぐっても、売買・トレードの具体的な戦術にはつながりません。
ほとんどの投資関連情報が、直近過去の後講釈です。
役に立ちません。
では、なぜ、オトナがオトナに向けて、役に立たない情報を発信しているのか?
なぜ、そんな構造があるのか……。
理由は、実社会と金融マーケットの“温度差”です。
学校でも社会でも、「事象には理由がある」「説明が可能」といった前提で話が進みます。これが、一般社会の常識です。相場の世界では全く別のジョーシキがあるのですが、それを説明するよりも、誰もが受け入れる、わかりやすい情報を発信したほうがビジネス的に正解なのです。
だから、株価が動いた理由なんてわからないのに、ビシッとした言葉で解説するのです。
あたかも、すべてのマーケット参加者に質問して、100%のホンネを聞き出したかのように。
そして、そんな“つくりものの情報”が見事に受け入れられるのです。

「半導体」というテーマ
「半導体関連が○○」みたいな解説は、よく目にします。
でも、半導体関連といっても、企業によって業績はまちまち、政策などに変化があったときの影響もさまざまです。「半導体関連だから見込みあり」というだけでは、オトナの分析とはいえません。
半導体関連の銘柄がそろって下落すると、「半導体の相場はバブルだった」なんて言葉が踊るのですが、こういうのも無責任な後講釈です。前述したように、企業によってバラバラですが、半導体そのものは今後も長い間、経済の中心的な存在でしょう。そうした前提があって、誰もが知っていて、そのうえで相場の上げ下げがある、企業ごとに評価が異なる、というのが現実です。
表面的な捉え方を売買に直結させるのが、今回のタイトルとして掲げた「材料張り」です。
言葉を素直に受け止めたら「材料を分析してポジションを取る戦略」ですが、短絡的に行動するという意味で否定的な表現です。
材料張りの姿勢で勝ち残る人は、いないでしょう。
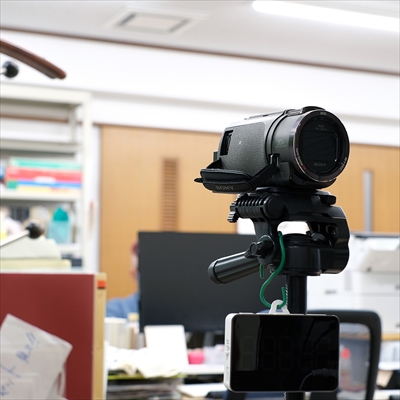
相場は相場に聞け
どんな理論があろうが、いわゆるマーケットの人気で動く株価に、自分のポジションが合致していなかったら利益にはなりません。
「相場は相場に聞け」といわれるゆえんです。
たとえ95%の確率で当たる株価上昇の予測であっても(そんな高確率はあり得ないのですが……)、実際に買って残り5%の見込み違いだったら、「株価変動と手が合っていない」と判断して、とにかくいったん切るしかないのです。
前項で「世間の常識は通用しない」と述べましたが、「努力すれば状況を変えられる」という常識も、やはりマーケットでは全く通用しないのです。値動きは、完全にマーケット任せです。
だから、中源線のように、予測の的中を求めず、値動きの変化をブレない基準で判断しつつ、慎重かつ丁寧な3分割の売買をするといった発想が、実践者に愛されているのです。「極めて現実的で実用的である」と認識されるのです。
「結局は値動きしだい」という現実に目を向けていれば、私が説いた“世間の常識とマーケットのジョーシキ”に自然と気づくし、たとえスタートが材料張りの発想でも、足りない部分を補う適正な思考が展開されるはずです。