株価が下げる過程で、丁寧に対応した。
うまくナンピンした。
でも、下げ止まらない・・・
相場あるあるの状況です。
あなたは、なにを基準に次の一手を考えますか?
「こんなときどうする」シリーズ第4回は、「ナンピンしたが下げ止まらない」という状況を分析してみました。
株価が下げる過程で、丁寧に対応した。
うまくナンピンした。
でも、下げ止まらない・・・
相場あるあるの状況です。
あなたは、なにを基準に次の一手を考えますか?
「こんなときどうする」シリーズ第4回は、「ナンピンしたが下げ止まらない」という状況を分析してみました。
今日の株式市場は全体に売られ、新型コロナウイルスの新たな変異株が取りざたされていますが、ざっくりと見て春から下げてきた株価が、そろそろ下げ止まってもいいころです。
今日は、下げつづけている銘柄を取り上げ、緻密な観察と丁寧な逆張り仕込みに目を向けた内容です。
持っている株がストップ高すれば、評価益が一気に増加します。
「勝った!」と感じます。
でも、自分で対応を決めて行動に移さないかぎり、その評価益は「絵に描いた餅」のまま……
実践的かつ合理的な状況認識、行動指針を考えてみました。
株価指数は高値で安定、でも個別銘柄の動きは鈍い……
「オレの株だけ上がらない!」という声が聞こえてきます。
相場はどんな状況か?
そして、適切な対応は?
YouTubeで最近はじめたシリーズは、「こんなときどうする?」。
よくある状況を設定し、実践的かつ実用的なアイデアを紹介する動画です。
本日公開の「どうする」第2弾は、これです!
ポジションを抱えて暴落
暴落がなくても、ふだん「ポジションを見直す」ときに使える方法を解説しました。
相場の環境は決してわるくありません。
株価指数は、10月上旬以降、上げトレンドを維持しています。
でも、個別株の動きは私たち投資家を振り回すような気まぐれ・・・
今日は、中源線の分割売買ルールを説明しながら、実践的な対応のアイデアをお届けします。
買った株が下がった、どうもよろしくない……
いま損切りすれば手堅い、でも切ったとたんに上昇するかもしれない。
ほんとに「相場あるある」の状況です。
あなたは、どう考えますか?
この迷いを解決するための思考、正解を出すためのアイデアを考えてみましょう!
自民党勝利で買い安心感の広がった株式市場。
でも、個別銘柄を見ると波動はバラバラで、「ついていくのが難しい」と感じるかもしれません。
今日は、そろそろ下げ止まりそうな銘柄、上昇トレンドの崩れていない銘柄から、押し目買いできそうなものをピックアップして紹介しました。
目玉の情報は、もちろん最後の「まとめ」。
すぐに役立つ実践のアイデアをお伝えします!
衆院選が終わり、結果は自民党の勝利。
でも、政治安定で株高というシナリオがすんなり実現するほど、マーケットは明るくないようです。
今回は「ダメな玉を切ってしまう」という実践論をテーマに掲げましたが、必要な行動を実行するには、脳内の情報がきれいに整理されている必要があります。
現在の相場を考えながら、相場における情報整理を見直してみましょう。
映像は、「YouTubeチャンネル「マーケット・スクランブル」」でご覧ください。
ダメ玉は切れ! 明暗がくっきり分かれる日本株
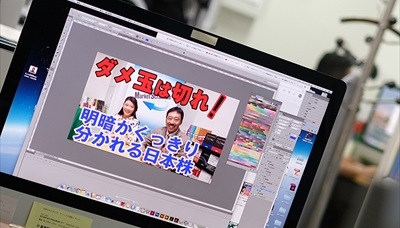
衆院選が終わって、相場にも新しい流れが生まれると期待しますよね。
ものすごく冷静な人でも、少し先の状況を予測して自分なりのシナリオを考え、ちょっとワクワク感が芽生えたりするでしょう。ところが、そんな気持ちを裏切ってくれるのが現実の相場。
今年は、イヤな裏切られ方を何度も味わって心が折れる……そんなケースが多いかもしれません。NYダウは新高値を更新して順調に伸びているのに、日本の株は元気がありません。
どうしても、イライラが蓄積されます。
そして、値動きに裏切られた結果の「しこり玉」も蓄積されます。
そんな状況で適切な“次の一手”とは?
これが、私たち実践者の課題です。
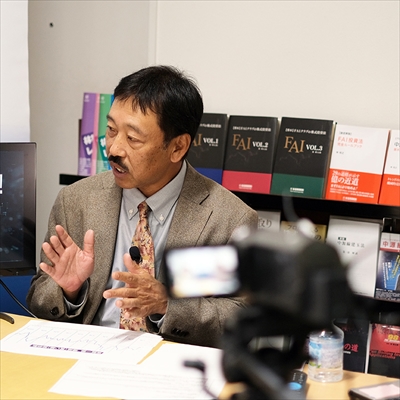
私は、株式市場について楽観的な見通しをもっています。
一貫して、強気の姿勢です。
だから、裁量の売買は買い戦略が軸です。
そして、春の上昇でまずまずの利益が上がりました。
ところが、動く銘柄が限られているので、そのあとの利益積み増しには至りません。
現在、コツコツと買っていますが、動きかけたと思うとしぼむ、という小さな裏切りにイライラが少したまっている状況です。かなりおとなしく売買しているのでイライラも許容範囲ですが……。
中源線の売買も現在、かなり難しいと思います。
動意づいたと思ったら出損なう、といった動きは、中源線のポジションをしっかりと裏切ってくれます。
取り損ないをいとわずに株数を抑えたり、増し玉せずに手仕舞いしてマル(ポジションなし)のまま次の展開を待っていたりと、お茶をにごすような対応をしています。
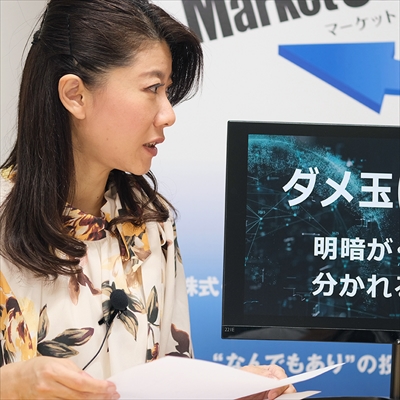
でも、いじけているだけでは前に進みません。
春からダラダラとそれなりに下げた銘柄も、決して少なくありません。どっちつかずの銘柄は多数あります。
そんななか、強気の私としては、微妙な変化をみせる銘柄に目が向きます。上昇がつづきそうな銘柄を探します。番組でのコメントは私のホンネですが、あくまでも「現時点での個人的な見解」です。翌日には変化している可能性もあるのです。
林投資研究所のオリジナルトレンド判定システム「中源線」の判断がそうであるように、見通しが売りから買いへ真逆に変わることもあり得ます。
ただ通常の場合、根底の見通しそのものは、それほどコロコロと変化しません。
細かく変化しうるのは、ポジションの状態です。
実際に値動きがわるければ、「おかしいなぁ」とつぶやきながら買いポジションを減らしたり、いったんゼロにして“入り直し”を狙ったりと、適度に変化させるのがふつうです。
こういったことが相場の実践ですから、「林の予測が当たるかもしれない」みたいな期待、決め打ちするイメージをもたずに話を聞いてくださいね。

値動きについてのコメントは、常に「その時点での個人的な見解」と述べました。
相手が相場なので、見通しはどうしたって流動的になります。
朝令暮改でも当然です。
ただ、前項で触れたように、ポジションを変化させながらも、一定期間のトレンドに目を向けていれば、見通しそのものが強気から弱気、再び弱気から強気と節操なく変わったりしません。
一方、つい頼りにしてしまう、新聞などの市況解説は、一貫性がなさすぎます。
その理由は明白。
「実践者のホンネ、プレーヤーの見通し」ではなく、極めて短期間の値動きを取り上げ、「誰もが納得しそうな理由」を上手に並べた“読みもの”だからです。
菅前総理の辞任表明、自民党の総裁選、そして衆院選とつづくなか、つかみどころのない値動きを政治と結びつけた解説がたくさんありました。でも、注意していると、矛盾する点も多々あったと思います。
研究がシゴトの経済学者、現場の人と多く接する経済記者、自分のカネを動かすトレーダー。
誰も、未来のことは知りません。同じ条件で株価を予測したら、結果は五十歩百歩かもしれません。
ただ、「見通し」という結論を出して言葉にする目的が大きく異なります。
こういった点を意識すれば、雑音に惑わされることなく、株を売買する実践者、プレーヤーとして見通しを立てることができますし、そのための情報整理も適切なものになるでしょう。

次回は11月8日、第2週なのでテーマ別の番組をお届けします。
タイトルは「どっちつかずの銘柄を選別して買う戦術」。
方向感のない往来をみせる銘柄が多い状況ですが、丁寧に観察して細かい変化を見つける発想を紹介する予定です。
お楽しみに!
2020年12月新刊